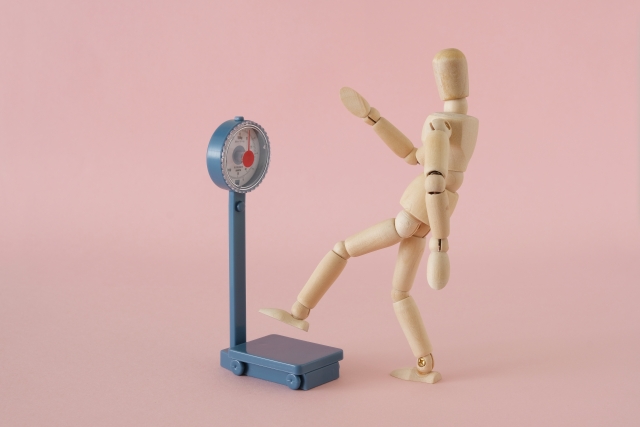
パワーリフティング競技における「水抜き」は、試合直前の検量(体重測定)をクリアするために、一時的に体内の水分を排出し、体重を意図的に落とす減量方法です。
筋肉量を維持したまま階級リミットをパスし、試合当日はより重い体重でパフォーマンスを発揮することを目的とします。
しかし、水抜きは身体に大きな負担をかけ、パフォーマンスの低下や深刻な健康被害につながる危険性も伴います。
実施する場合は、その原理とリスクを十分に理解し、専門家や経験豊富な指導者のもとで慎重に行うようにしましょう。
水抜きの基本原理
水抜きは、主に以下の2つの身体の仕組みを利用します。
利尿作用のコントロール
事前に大量の水分を摂取することで、体は水分を排出しやすい状態(抗利尿ホルモンの分泌が抑制された状態)になります。
その後、水分摂取を急に制限することで、体は水分を排出するモードのままとなり、摂取量以上に水分が排出されて体重が減少します。
塩分(ナトリウム)と水分の関係
ナトリウムは体内で水分を保持する働きがあります。
そのため、水分を排出する段階で塩分摂取を厳しく制限することで、より効率的に体内の水分を排出させることができます。
水抜きの具体的なスケジュールと手順
ここでは、一般的なスケジュール例を紹介します。
なお、減量幅や個人の体質によって調整が必要です。
パワーリフティングでは当日計量(検量から試合まで約2時間)が一般的です。
パフォーマンスへの影響を最小限に抑えるため、水抜きによる減量幅は体重の3%以内が安全な目安とされています。
大会7日前〜3日前:ウォーターローディング期
身体を「水分を排出しやすい状態」にする時期です。
水分摂取
1日に体重の8〜10%を目安に、普段より多くの水分(例: 体重80kgなら6.4ℓ〜8ℓ)を摂取します。
尿の色が透明に近くなるのが一つの目安です。
塩分摂取
1日に10g以上を目安に、意識的に塩分を多く摂取します。
大会2日前:塩抜き期
体内から塩分を抜き、水分排出を促します。
水分摂取
ウォーターローディング期と同様に、多くの水分(6ℓ〜8ℓなど)を摂取し続けます。
塩分摂取
1日2〜4g以下に厳しく制限します。
加工食品を避け、調味料を使わない食事が基本です。
糖質摂取
筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンを枯渇させないため、食物繊維の少ない糖質(白米、うどんなど)を体重1kgあたり1〜2g程度摂取します。
大会前日:ウォーターカット(水抜き)期
本格的に水分を排出し、体重を落とします。
水分摂取
水分摂取を大幅に制限します。
例えば、「検量の16時間前までに体重1kgあたり15ml(体重80kgなら1.2ℓ)を飲み終える」といった方法があります。
塩分摂取
引き続き塩分は厳しく制限します。
糖質摂取
前日と同様に食物繊維の少ない糖質(白米、うどんなど)を体重1kgあたり1〜2g程度摂取します。
発汗促進(必要な場合)
体重の落ちが悪い場合、半身浴やサウナで発汗を促します。
しかし、脱水症状のリスクが非常に高まるため、細心の注意が必要です。
大会当日:検量とリカバリー
検量をパスし、試合までに回復します。
検量前
会場への移動などで自然に200〜500g程度体重が落ちることもあります。
最後の微調整を行います。
検量後
ここからの2時間が非常に重要です。
パフォーマンスを最大限発揮するためのリカバリーを行います。
ウォーターローディング期の塩分摂取について
日本人の平均的な食塩摂取量は1日あたり約10gと言われています。
つまり、普段通りのしっかりとした味付けの和食を3食とると、概ね10gに近い塩分量になります。
しかし、ウォーターローディングの目的は「意識的に普段より多く」塩分を摂ることなので、具体的な食品の塩分量を知っておくと目標を達成しやすくなります。
食事から摂取できる塩分量のイメージ
以下の内容で約5.0gの摂取となります。
- ごはん
- 味噌汁(インスタントも可):約1.5g
- 納豆(タレ含む):約0.7g
- 塩鮭(甘塩・1切れ):約0.8g
- 梅干し1個:約2.0g
食品・調味料の塩分量目安
調味料
- 食塩(小さじ1杯):6.0g
- 濃口しょうゆ(大さじ1杯):2.5g
- 味噌(大さじ1杯):2.0g
- めんつゆ(3倍濃縮)(大さじ1杯):1.5g
食品
- 梅干し(中1個):2.0g
- たらこ(1/2腹):2.5g
- 塩鮭(甘塩)(1切れ):0.8g
- 魚肉ソーセージ(1本):2.5g
- プロセスチーズ(1個):0.7g
- インスタント味噌汁(1杯):1.5~2.0g
- カップラーメン(1個):5.0~7.0g
効率的に10g以上の塩分を摂取する方法
ウォーターローディング期は、大量の水分(6ℓ〜8ℓなど)を摂取するため、体内の塩分濃度が薄まりがちです。
それを防ぎ、体に水分をしっかり保持させるために、以下の方法で効率的に塩分を摂取しましょう。
- 汁物を積極的に摂る
- 味噌汁、スープなどは塩分を摂取しやすい代表格です。毎食に汁物を取り入れるだけで、かなりの塩分量を確保できます。
- 昆布茶や顆粒だしをお湯で溶いて飲むのも手軽な方法です。
- ごはんのお供を活用する
- 梅干し、たらこ、塩昆布、漬物、佃煮、なめたけなどを食事にプラス一品加えることで、手軽に塩分を補給できます。
- 調味料を「ちょい足し」する
- 調理済みの料理(炒め物、サラダ、冷奴など)に醤油や塩を少しだけ追加します。
- トレーニング後のプロテインに、ひとつまみの塩を入れるのも効果的です。
- 電解質ドリンクやサプリメントを利用する
- 大量の水分摂取が辛い場合や、食事だけで目標に届かない場合に有効です。
- 経口補水液
水分と塩分を効率よく吸収できるように設計されています。 - 塩分タブレット・塩飴
トレーニング前後や食間に手軽に摂取できます。
製品によって塩分含有量が違うので、表示を確認しましょう。
- 水分と塩分をセットで摂取する
- 重要なのは、こまめな水分補給と同時に塩分も摂取することです。
- 例えば、コップ1杯の水を飲むタイミングで塩昆布を少しつまむ、といったようにセットで摂ることで、体内の電解質バランスを保ちやすくなります。
塩分摂取の注意点
普段、健康のために減塩を心がけている方にとっては、高塩分の食事は胃腸に負担がかかることがあります。
体調を見ながら調整してください。
この高塩分・高水分の食事法は、あくまで水抜きのための期間限定の特殊な方法です。
長期間続けると健康を害する恐れがあるため、必ず期間を守ってください。
ご自身の食生活や体調に合わせて、これらの方法を組み合わせて1日10g以上の塩分摂取を目指してください。
大会2日前・大会前日の食事について
パワーリフティングの試合直前の塩抜き期・水抜き期における糖質摂取は、非常に悩ましいポイントです。
「塩分と余計な水分を避けながら、どうやってエネルギー源である糖質を確保するか」がカギとなります。
以下に、そのための最適な食事法と考え方を詳しく解説します。
基本的な考え方:食事は「作業」と考える
まず、大会2日前と前日の食事は「楽しむもの」ではなく、「検量と試合のための作業」と割り切ることが重要です。
味気なくても、目的を達成するための燃料補給と捉えましょう。
目的:
- 塩分(ナトリウム)を徹底的に排除することで、体の水分排出を最大限に促す。
- 食物繊維を避けることで、消化管に留まる内容物と水分量を減らし、体重を軽くする。
- 筋肉のグリコーゲンを維持するために、消化の良い糖質を最低限摂取し、試合でのエネルギー切れを防ぐ。
最適な食事方法の詳細
①主食(糖質源)の選び方
以下の「低食物繊維・高糖質」な食材を食事のベースにします。
- 白米:最も基本となる食材です。玄米や雑穀米は食物繊維が多いためNGです。
- 餅(もち): 白米を凝縮したもので、少量で効率よく糖質が摂れます。塩の入っていないものを選びます。
- うどん(乾麺・生麺):汁なしで食べます。
- そばは食物繊維が多めなので、うどんの方が適しています。
- パスタ:デュラムセモリナ100%のもの。ソースなしで食べます。
- じゃがいも:皮をむいて蒸すか、茹でるのが良いです。
- フライドポテトは塩分が多いのでNG。
食パンやロールパンは、ほとんどの製品に塩分が含まれているため、避けるのが無難です。
②「おかず」と「味付け」
「塩辛いおかずでご飯を食べる」という発想を捨てましょう。
A. 甘い味付けで糖質を摂取する(最も簡単で効果的)
塩分を全く含まず、純粋な糖質を補給できるため、多くの選手がこの方法を取り入れています。
- 白米や餅にかける・つける
- はちみつ
- メープルシロップ
- ジャム
- あんこ(無塩のもの)
- 砂糖ときな粉
- きな粉は大豆製品ですが、少量なら問題ありません
B. 塩分を含まない調味料で風味をつける
甘いものが苦手な場合や、少しでも変化をつけたい場合の選択肢です。
- 無塩バター、オリーブオイル:茹でたパスタや蒸したじゃがいもに和える。
- 胡椒(こしょう):あらゆるものに使えます。
- 各種スパイス・ハーブ:ガーリックパウダー、パプリカパウダー、バジル、オレガノなど。
- 市販のミックススパイスには塩が含まれていることが多いので、必ず成分表示を確認してください)
- レモン汁、お酢:風味付けに使えます。
- ごま、青のり
C. おかずを食べる場合
どうしても固形物が食べたい場合は、「味付けなしで調理した食材」に限られます。
- 鶏胸肉、ささみ:塩・コショウなしで茹でるか蒸したもの。
- 卵:味付けなしのゆで卵、または無塩バターで作った炒り卵。
絶対に避けるべきもの(NGリスト)
- 味噌汁、スープ、ラーメンの汁:塩分と水分の塊です。
- 醤油、味噌、ソース、ケチャップ、マヨネーズ:主要な塩分源です。
- 加工食品全般(ハム、ソーセージ、チーズ、練り物):大量の塩分を含んでいます。
- 漬物、梅干し、佃煮:塩分の塊です。
- 市販の惣菜、外食:ほぼ全てのメニューに塩分が使われています。
- スポーツドリンク:ナトリウム(塩分)が含まれているためNGです。
この2日間の食事は、検量をパスし、試合で最高のパフォーマンスを発揮するための最終調整です。味気ない食事になりますが、目的意識をしっかり持って乗り切りましょう。
ライスケーキを活用する
欧米で一般的に食べられている、円盤状に薄く膨らませたお米のスナック「ライスケーキ」というものがあります。
ライスケーキは、パワーリフティングの水抜き期の食事として非常に優れた選択肢です。
特に、水分摂取を厳しく制限する大会前日には、白米や餅以上に最適な食材と言えます。
ライスケーキは、輸入食品店や、最近では大きめのスーパーマーケットで手に入ります。
ライスケーキが水抜き期に最適な理由
ライスケーキには、この時期の食事に求められる条件を完璧に満たす多くのメリットがあります。
- 塩分を完全にコントロールできる
- ライスケーキには「プレーン(無塩)」タイプと、塩などで味付けされたものがあります。「プレーン」を選べば、塩分をほぼゼロに抑えることが可能です。これは、おかずや調味料を一切使えないこの時期において最大の利点です。
- 消化が良く、食物繊維が非常に少ない
- 白米を膨らませて作られているため、消化器官への負担が少なく、体内に余計なものが残りません。玄米(ブラウンライス)でできたものではなく、白米(ホワイトライス)のものを選ぶようにしましょう。
- 純粋な糖質源として計算しやすい
- ほとんどが炭水化物で構成されており、製品にもよりますが1枚あたり約7〜8gの糖質が含まれています。そのため、「今日はあと糖質を30g摂りたいから、ライスケーキを4枚食べよう」といったように、摂取量を非常に正確に管理できます。
- 水分量が極めて少ない
- これが白米や餅に対する最大のメリットです。調理に水分を必要とせず、製品自体の水分含有量もほぼありません。水分摂取を1滴でも減らしたい最終日に、重量を増やすことなく糖質だけを摂取できるのは非常に大きいです。
- 手軽さと満足感
- 調理不要でそのまま食べられます。また、水分を制限している時は口の中が寂しくなりがちですが、ライスケーキのパリパリとした食感は空腹感や口寂しさを紛らわすのに役立ちます。
ライスケーキの具体的な使い方
「甘い味付けで糖質を摂取する方法」と組み合わせるのがベストです。
ライスケーキに、はちみつやジャム、メープルシロップを塗って食べる。
この方法なら、塩分と余計な水分を完全に排除しながら、必要な糖質を的確に摂取できます。
ライスケーキの注意点
必ず「プレーン」「ソルトフリー(無塩)」と書かれた製品を選んでください。
チーズ味やコンソメ味などは大量の塩分を含んでいるため絶対にNGです。
ライスケーキをうまく活用することで、大会直前の厳しい食事制限をよりスマートに、そして効果的に乗り切ることができます。
まさにパワーリフターの減量末期の力強い味方です。
大会2日前・大会前日の糖質の摂取方法
大会2日前と大会前日の糖質摂取の目標量(体重1kgあたり1〜2g)は同じですが、その食べ方、タイミング、そして食材の選び方に対する注意レベルが異なります。
大会前日は、単に塩分を抜くだけでなく、体内の水分を積極的に排出させる「ウォーターカット」の最終段階に入るため、より緻密な戦略が必要になります。
大会2日前 – 塩抜き期
- 目的:塩分を抜きつつ、筋肉のグリコーゲン(エネルギー)は維持する
- 水分:まだ多めに摂取している(例: 7ℓ以上)
- 食事のポイント:
- 塩分ゼロ、低食物繊維を守れば、ある程度通常の食事に近い形で糖質を摂取できる。
- 白米やうどんなど、調理に水分を使うものでも問題ない。
- 1日3食に分けて、比較的普通の時間に食べることができる。
具体的な食事メニュー例
体重80kgの選手の場合、目標糖質量:80kg × 1.5g = 120g/日 となります。
この日はまだ水分を多めに摂取します(例:7ℓ〜8ℓ)。
- メニュー①(糖質 約55g)
- 白米 150g
- 味付け:はちみつをたっぷりかける
- (もし食べるなら)塩なしで茹でた鶏ささみ 1本
- メニュー②(糖質 約50g)
- 茹でたうどん 1玉
- 味付け:オリーブオイルと黒胡椒で和える
- メニュー③(糖質 約50g)
- 切り餅 2個
- 味付け:焼いて、砂糖ときな粉をまぶす
大会前日 – ウォーターカット(水抜き)期
- 目的:体重に影響する全ての要素を最小限に抑えつつ、グリコーゲンは枯渇させない。
- 水分:摂取を大幅に制限している(例: 1ℓ以下、あるいは特定の時間以降は完全にカット)。
- 食事のポイント:
- 「固形物の重量」を意識する
- 食べた物そのものにも重さがあります。消化管に残る内容物を極力減らすため、食事のタイミングが非常に重要になります。
- 「食品に含まれる水分」を意識する
- ご飯やうどんは調理過程で水分を多く含みます。水分摂取を厳しく制限している中では、この食品由来の水分も無視できません。
- 「固形物の重量」を意識する
具体的な食事メニュー例
体重80kgの選手の場合、目標糖質量:80kg × 1.5g = 120g/日 となります。
この日は水分摂取を大幅に制限します(例:1ℓ以下)。
そのため、食事からの水分も極力減らします。
食事の考え方
調理に水を使わない、もしくは水分が飛ぶものが望ましいです(焼く、など)。
喉が渇きにくいように、食事を複数回に分けて少量ずつ摂るのも有効です。
食事メニュー例
以下で、糖質 約120g です。
- 餅1個を焼いてメープルシロップで食べる。(糖質 約25g)
- 白米のおにぎり(塩なし・具なし)100g。(糖質 約37g)
- 蒸して水分を飛ばしたじゃがいも中1個に無塩バターを乗せる。(糖質 約30g)
- 餅1個を焼いて食べる。(糖質 約25g)
比較表:大会2日前 vs 大会前日の糖質摂取
| 項目 | 大会2日前 – 塩抜き期 | 大会前日 – 水抜き期 |
|---|---|---|
| 目標糖質量 | 体重1kgあたり1〜2g | 体重1kgあたり1〜2g |
| 主な目的 | グリコーゲン維持、塩分排出 | グリコーゲン維持、総重量の最小化 |
| 水分摂取 | 多い (例:7ℓ以上) | 非常に少ない (例:1ℓ以下) |
| 推奨食材 | 白米、うどん、餅、パスタなど | ライスケーキ、餅 が最適。白米も可。 |
| 食事の考え方 | 1日3食、通常の食事に近い感覚 | 消化管を空にすることを意識する |
| 最後の食事 | 夜、通常の時間に食べてもOK | 検量の14〜18時間前には終える。 |
大会前日のより具体的な糖質摂取戦略
食材の選択:より「ドライ」なものへ
大会2日前以上に、水分含有量が少なく、消化の良い食材が理想です。
- 最有力候補
- ライスケーキ(無塩):軽くて水分が無く、糖質量が計算しやすいため最強の選択肢です。
- 餅(もち):焼いて水分を飛ばして食べます。白米よりも少ない体積で糖質を摂取できます。
- 次善の選択肢
- 白米:食べる場合は、普段より硬めに炊く、あるいは一度炊いたものを冷まして少し水分を飛ばすなどの工夫が考えられます。
- 補助的な糖質源
- はちみつ、ジャム、メープルシロップ:ライスケーキや餅につけて食べます。純粋な糖質源です。
- ハードキャンディ(飴):最後の最後、口寂しい時や血糖値の低下を感じた時に、水分摂取なしで糖質を補給できます。
食事のタイミング:早めに終える
検量時間から逆算して、固形物の摂取を早めに切り上げます。
これは消化管の内容物を空にして、体重を少しでも軽くするためです。
一般的な目安としては、検量の14〜18時間前には固形物の摂取を終えます。
例えば、日曜日の朝9時に検量の場合、土曜日の午後3時〜5時頃には最後の固形物を食べます。
それ以降、もし空腹感が強い場合やエネルギー切れが心配な場合は、はちみつを少量舐める、飴を舐める程度に留めます。
土曜日の過ごし方は、検量当日の体重に直接影響します。
糖質の「量」は金曜日と同じでも、「質」と「タイミング」をより厳格に管理することが、水抜きを成功させるための最後のカギとなります。
大会2日前・大会前日のたんぱく質の摂取方法
たんぱく質の摂取に関しても、この期間は非常に重要な注意点があります。
炭水化物と同様に、「何を」「どれだけ」「いつ」食べるかを戦略的に考える必要があります。
この時期のたんぱく質摂取の目的は「筋肉を積極的に作ること」ではなく、「筋肉の分解を防ぎつつ、体重増加のリスクを最小限に抑えること」です。
大会2日前・前日のたんぱく質摂取における最重要原則
- 摂取量を減らす
- 通常のトレーニング期(例:体重1kgあたり2g)よりも摂取量を減らします。体重1kgあたり1.2g〜1.6g程度を目安にすると良いでしょう。
- たんぱく質の消化・代謝には水分が使われるため、摂取量を減らすことで水抜きを助ける側面もあります。
- 塩分を徹底的に排除する
- 多くのたんぱく質源には、加工の過程や調理で塩分が加えられます。味付けなしで調理された、素材そのものを食べる必要があります。
- 消化の良い、低脂質なものを選ぶ
- 脂質は消化に時間がかかり、胃腸に長く留まるため、検量時の体重に影響します。
- 鶏むね肉や白身魚などの「リーン(低脂質)」な食材が最適です。
- プロテインパウダーは要注意
- 多くのプロテインパウダーには、味を調えるためにナトリウム(塩分)が含まれています。また、水分で溶かして飲むため、水分制限をしている前日には計算が複雑になります。
- もし利用する場合は成分表示を必ず確認し、無添加・低ナトリウムのものを選びましょう。
- 基本的には固形物から摂る方が無難です。
【具体的に何を食べるか】推奨されるたんぱく質源
非常に推奨される(Best Choices)
- 鶏むね肉(皮なし)、ささみ
- 低脂質・高たんぱくの代表格。
- 調理法は「茹でる」か「蒸す」のが最も確実です。
- 塩・コショウなどの調味料は一切使わず、調理したものをそのまま食べます。
- 白身魚(タラ、カレイ、ティラピアなど)
- 鶏肉と同様に非常に低脂質で消化が良いです。
- これも茹でるか蒸して食べます。
- 卵白(卵の白身)
- ほぼ純粋なたんぱく質で、脂質が含まれる卵黄を避けることで、よりリーンになります。
- 味付けなしの炒り卵や、茹でて白身だけ食べるなどの方法があります。
避けるべき、または注意が必要なたんぱく質源
- 絶対に避けるべきもの (NG List)
- 加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ):塩分の塊です。
- チーズ、乳製品:ほとんどのチーズに塩分が含まれています。
- 缶詰の魚(ツナ缶、サバ缶など):保存のために塩水や油(塩分添加)に漬けられています。
- 干物、塩鮭など:塩分が非常に多いです。
- コンビニのサラダチキンなど:便利ですが、ほぼ全てのものに塩分が含まれています。
- できれば避けたいもの (Less Optimal)
- 赤身肉(牛肉、豚肉):脂質が多く、消化に時間がかかります。
- 青魚(サバ、イワシ、サンマなど):良質な脂質ですが、この時期は消化の負担を考えて白身魚を選びましょう。
- 大豆製品(納豆、豆腐):食物繊維が多く、納豆はタレに塩分が含まれるため不向きです。
たんぱく質の摂取は刺身でもよいか?
結論から言うと、刺身で食べることは原則として非推奨であり、避けるのが賢明です。
理論上、塩分を含まない新鮮な白身魚の刺身そのものは、低脂質・高たんぱくの条件を満たします。
しかし、大会直前の極めてデリケートな時期においては、調理(加熱)する場合と比較して、看過できないいくつかの大きなリスクとデメリットが存在します。
刺身が推奨されない3つの大きな理由
1. 塩分(醤油)の問題
刺身を食べる上で、醤油を完全に避けることは非常に難しいです。
そして、醤油は「塩分の塊」です。 ほんの少し醤油をつけただけでも、数グラムの塩分を容易に摂取してしまい、それまで数日間かけて行ってきた「塩抜き」の努力がすべて台無しになってしまいます。
体は再び水分を保持しようと働き始め、水抜きが計画通りに進まなくなるリスクが極めて高くなります。 このリスクは、刺身の味や食感というメリットをはるかに上回ります。
2. 食中毒のリスク【最も危険な理由】
これはコンディション管理において致命的なリスクです。
生魚には、どれだけ新鮮に見えてもアニサキスや細菌が付着している可能性がゼロではありません。
もし大会の前日や前々日に食中毒になってしまった場合、腹痛、嘔吐、下痢といった症状に見舞われます。
脱水症状がコントロール不能になり、検量どころではなくなります。
仮に検量をパスできたとしても、体内の電解質バランスは崩壊し、パフォーマンスは壊滅的な状態になります。
試合という最高のパフォーマンスを発揮すべき舞台の直前に、このようなコントロール不可能なリスクを冒す必要は全くありません。 加熱調理(茹でる、蒸す)は、このリスクをほぼ100%排除できます。
3. 消化の観点
一般的に刺身は消化に良いとされていますが、人によっては生のたんぱく質が胃腸の負担になることもあります。
それに対し、加熱されたたんぱく質は組織が部分的に分解されているため、より消化しやすい状態になっています。
水抜きで体も胃腸もストレス下にある状態では、少しでも消化が確実で、体に負担の少ない調理法を選ぶのがセオリーです。
結論:リスクを徹底的に排除する
大会2日前と前日の食事管理で最も優先すべきことは、「余計な変数をなくし、リスクを徹底的に排除すること」です。
| 刺身(生食) | 茹でる・蒸す(加熱) | |
| 塩分リスク | 非常に高い(醤油の使用) | ゼロにコントロール可能 |
| 食中毒リスク | ゼロではない | ほぼゼロにできる |
| 消化の確実性 | 個人差あり | より確実で安定的 |
刺身を食べたいという気持ちは理解できますが、その選択がもたらす可能性のある最悪の事態(検量失格、パフォーマンスの崩壊)を考えると、そのリスクはあまりにも大きすぎます。
「茹でるか蒸した、味付けなしの鶏むね肉・ささみ・白身魚」。
これは、多くのトップ選手が実践する、最も安全で確実な方法です。
味気ないかもしれませんが、最高の状態で試合に臨むための最後の重要な「作業」と捉え、安全な選択をすることを強くお勧めします。
時系列での戦略:大会2日前と前日の違い
大会2日前 – 塩抜き期
- この日はまだ通常の食事に近い形でたんぱく質を摂取できます。
- 上記の「非常に推奨される」食材を、塩分なしで調理し、1日の目標量(体重1kgあたり1.2〜1.6g)を3食に分けて食べます。
大会前日 – 水抜き期
- 炭水化物と同様に、固形物であるたんぱく質の摂取も早めに終えることが重要です。
- 消化管の内容物を空にするため、検量の14〜18時間前(例:土曜日の午後3時〜5時頃)には最後のたんぱく質摂取を終えるのが理想です。
- 量は金曜日より少し控えるか、同じ量をより早い時間帯にまとめて摂取するなどの工夫をします。
この2日間のたんぱく質摂取は、普段の感覚とは全く異なります。
「筋肉を増やす」という意識は一度忘れ、「いかに減量への悪影響をなくすか」という視点で、食材を選び、調理法を管理することが成功のカギとなります。
大会前のカフェインの摂取について
コーヒー(カフェイン)の摂取は多くのリフターが悩むポイントであり、各期間の目的によって「飲んでも良いか」「避けるべきか」の判断が全く異なります。
結論を先にまとめた表がこちらです。
| 時期 | 推奨度 | 目的と理由 |
| 大会 7日前〜3日前 | ◎ 問題なし | 利尿作用が水分排出の目的に合致する。 |
| 大会 2日前(金曜日) | ○ 概ね問題なし | 引き続き利尿作用はプラスに働くが、体調変化に注意。 |
| 大会 前日(土曜日) | △ 注意が必要 | 水分排出を加速させるが、脱水が進みすぎたり睡眠を妨害するリスクあり。 |
| リカバリー(検量後) | ✕ 直後は非推奨 | 再水和(リハイドレーション)を阻害するため。タイミングが重要。 |
以下で、各期間について詳しく解説します。
大会 7日前〜3日前(ウォーターローディング期)
【結論】ブラックコーヒーであれば、問題なく飲んでいただけます。
理由
この期間の目的は、大量の水分を摂取することで体を「水分を排出しやすいモード」にすることです。
コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があり、尿の排出を促します。
これは、この期間の目的と合致しており、むしろポジティブに働く可能性があります。
注意点
- 必ずブラックコーヒーにしてください。砂糖やミルク、クリームは不要なカロリーや脂質、糖質であり、減量の妨げになります。
- コーヒーを水分摂取量にカウントするのは避けましょう。あくまで「6〜8Lの水」とは別に、嗜好品として1〜2杯程度に留めるのが賢明です。
- 睡眠の質を落とさないよう、午後の遅い時間や夜に飲むのは避けましょう。
大会 2日前(金曜日)(塩抜き期)
【結論】ブラックコーヒーであれば、概ね問題ありません。
理由
この日もまだ大量の水分を摂取しているため、カフェインの利尿作用は水分排出を助ける方向に働きます。
注意点
- 塩分を抜いているため、体が少しずつストレスを感じ始めています。人によってはカフェインに過敏になり、不安感や胃の不快感を覚えることもあります。少しでも体調に異変を感じたら、すぐに中止してください。
- 7日前〜3日前と同様、ブラックで、睡眠に影響しない時間に飲むのが原則です。
大会 前日(土曜日)(ウォーターカット期)
【結論】上級者向けのテクニック。基本的には避けるのが無難です。
理由とリスク
この日は水分摂取を極端に制限します。ここでコーヒーを飲むと、その強力な利尿作用で水分排出がさらに加速します。これは体重を落とす上では「諸刃の剣」です。
メリット: 最後の数百グラムを絞り出す助けになる可能性がある。
デメリット
- 脱水のコントロールが難しい
- 必要以上に水分が抜けすぎてしまい、深刻な脱水症状(頭痛、めまい、痙攣リスクの上昇)に陥る危険性があります。
- 睡眠の質の低下
- 試合前夜の睡眠は極めて重要です。カフェインが睡眠を妨害するリスクは絶対に避けるべきです。
もし飲む場合
経験豊富な選手が、午前中の早い時間に少量のエスプレッソなどを飲み、最後の水抜きを促すケースがありますが、初心者〜中級者の方は手を出さない方が安全です。
リカバリー(検量後〜試合開始まで)
【結論】検量直後に飲むのは絶対にNGです。飲むならタイミングが全てです。
検量直後に飲んではいけない理由
- この時間帯の最優先事項は「失われた水分と電解質を体に吸収させること(再水和)」です。
- カフェインの利尿作用は、この再水和のプロセスを著しく妨害します。せっかく飲んだ水分や電解質が、体に吸収される前に尿として排出されてしまうからです。胃腸に負担をかける可能性もあります。
正しいリカバリーでのカフェインの摂り方
カフェインは、筋力や集中力を高める非常に有効なエルゴジェニックエイド(運動能力向上サプリメント)です。
リカバリーで「使ってはいけない」のではなく、「使うタイミングが重要」なのです。
- 【最優先】まず再水和と栄養補給に集中(検量後〜約90分)
- 電解質ドリンクと糖質(おにぎり、大福、バナナなど)の摂取を最優先します。
- この段階でコーヒーは絶対に飲まないでください。
- 【戦略的摂取】試技開始の約45〜60分前
- 体の水分がある程度戻り、胃腸も落ち着いてきた段階で、パフォーマンス向上のためにカフェインを摂取します。
- 推奨される形態
- カフェイン錠剤
- 最もおすすめ。余計な水分や成分なしに、正確な量のカフェインを摂取できます。
- エスプレッソ(少量)
- 量が少ないため、利尿作用の影響を最小限に抑えつつ、カフェインを素早く摂取できます。
- エナジードリンク(飲み慣れたもの)
- カフェインと糖質を同時に摂れますが、炭酸による膨満感などが起きないか、事前に試しておく必要があります。
- カフェイン錠剤
- 避けるべき形態
- カップに入った大量のドリップコーヒー
- 水分量が多く、利尿作用を強く引き起こすため、このタイミングでは不向きです。
- カップに入った大量のドリップコーヒー
このように、コーヒー(カフェイン)は飲むタイミングによって味方にも敵にもなります。
各期間の目的を正しく理解し、戦略的に付き合っていくことが重要です。
【最後に】水抜きの危険性と注意点
水抜きは、計画通りに進まないと検量失格のリスクがあるだけでなく、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。
- パフォーマンスの低下
体重の3%を超える水分が失われると、筋力や集中力が著しく低下し、筋肉の痙攣(けいれん)を引き起こすリスクが高まります。 - 脱水症状
めまい、頭痛、吐き気などの症状が現れ、重篤な場合は意識障害や熱中症に至る危険があります。 - 臓器への負担
特に腎臓に大きな負担がかかり、急性腎障害などを引き起こす可能性があります。
繰り返すことで慢性的なダメージにつながることも指摘されています。 - 電解質バランスの異常
体内のミネラルバランスが崩れ、心臓に負担をかけることもあります。
そのため、以下について注意しましょう。
- 安易に手を出さない
初めての場合は特に、自己流で行うのは非常に危険です。
必ず専門家や経験豊富な指導者の下で行ってください。 - 体調を最優先する
少しでも異常を感じたら、すぐに中止してください。
大会に出場することよりも、ご自身の健康が最も重要です。 - 利尿剤の絶対禁止
利尿剤の使用はドーピング違反であると同時に、体を危険な脱水状態に陥らせるため、絶対にやめてください。
水抜きは、競技成績を向上させる可能性のあるテクニックですが、それは緻密な計画と自己管理、そして何よりも安全が確保されて初めて成り立つものです。
そのリスクを十分に理解した上で、慎重に取り組むようにしましょう。